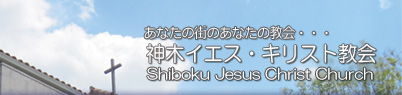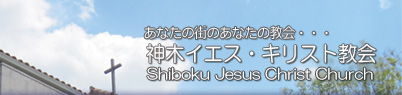●「太陽と風」の物語
イソップ童話に『太陽と風』という話がある。あるとき北風と太陽は互いに力自慢をする。いくら自慢し合ってもらちがあかないので、あの旅人が着ているコートをどちらが早く脱がせられるかを競い合った。まずは北風が、ありったけの風を吹いてみせた。ところが、風を吹かせれば吹かせるだけ旅人はコートの襟を立て、コートをしっかりと両手で押さえた。そこで太陽の出番となり、太陽は暖かな光を一面に注ぎだした。旅人は急に暖かくなったのでコートを脱いだ。北風は負けたと言いながら去って行った。
なぜ『太陽と風』の話を持ち出したかというと、人が人を動かそうとするとき、相手を力尽くで動かそうとする場合と、相手を愛することで動かそうとする場合とがあることを知ってもらうためだ。前者を「恐れの原理」を使うといい、後者を「愛の原理」を使うという。『太陽と風』の話は、この二つの違いを見事に描いている。
そこで今回のコラムだが、私たちの信じているキリストは、人をどのように動かそうとするのかを見ていきたい。無論、キリストは「愛の原理」を使い、人を動かそうとされる。神の福音の根底にあるのは、あの『太陽』と同じであり、人を無条件で愛する神の愛がある。
天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
(新約聖書 マタイの福音書 5:45)
クリスチャンであれば、そんなことは当たり前だと言うかもしれない。しかし、現実は「愛の原理」に支えられているはずの神の福音を、私たちはいつの間にか「恐れの原理」で支えようとしてはいないだろうか。実はしてしまっている。この世界は「恐れの原理」で成り立っているから、どうしても神の福音の中にもそれが入り込んでしまう。そうした現状から見ていこう。
●l 「恐れの原理」の現状
「賞罰教育」という言葉を聞いたことがあるだろう。良い成績を取れば賞を与え、悪いことをすれば罰を与えるという教育である。この教育の下では、人は罰を避けようと一生懸命に頑張る。これが恐れさせることで人を動かそうとする、典型的な「恐れの原理」である。
この世界は、まさに「恐れの原理」によって人は動かされている。親は子どもに罰をちらつかせ、子どもを動かそうとする。会社では、上司が出世や罰をちらつかせることで部下を動かそうとする。人は誰であれ、周りの評判を恐れて行動してしまう。人は絶えず脅され、絶えず恐れを覚えながら行動している。それが、この世界にほかならない。その原理を一言で言うと、「何々が欲しければ、○○をしろ」である。これの裏返しが、「幸せになれないのは、○○をしないからだ」、あるいは「災いに遭うのは、○○をしないからだ」となる。
宗教は、そうした「恐れの原理」を使い、「何々が欲しければ、○○をしろ」と人を脅し、人を操ろうとする。当然、この原理はキリスト教の中にも入り込んだ。「神の救いが欲しければ、○○をしろ」といった教えになって現れた。これを「律法主義」というが、その典型的な教えが、人が義とされ救われるのは「律法の行い」によるというものだった。無論、これは誤った教えなので、パウロは、「人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが、私たちの考えです」(ローマ3:28)と言って戦った。「恐れの原理」は、他にも様々な形で神の福音を変えてしまった。
例えば「神の祝福が欲しければ、○○しなければならない」と言うのも、例えば「終わりの日は近い。だから○○しなければならない」と言うのも、神の福音を「恐れの原理」で支えてしまっている。あるいは、行いが良い熱心なクリスチャンを称賛するのも同様である。それは、あなたは頑張らないから称賛されないという見事な脅しになり、周りの目を恐れさせてしまう。そうなると、教会では互いを比べて裁き合うことが頻発し、この世と何ら変わらない動機で交わる集団を育ててしまう。神の福音が、「恐れの原理」に支えられてしまう。
どうだろう。あなたはクリスチャン生活を、「恐れの原理」の中で過ごしてはいないだろうか。クリスチャンであればこうしなければならないという恐れから、頑張っているのではないだろうか。絶えず周りの目を恐れ、「クリスチャンは、○○でなければならない」と自らに言い聞かせながら過ごしているのではないだろうか。こうした恐れから生まれる「ねばならない」という思いを「律法」といい、人は恐れから「律法の文字」に仕えてしまう。聖書は、そんな生き方をやめるよう促している。
神は私たちに、新しい契約に仕える者となる資格を下さいました。文字に仕える者ではなく、御霊に仕える者です。文字は殺し、御霊は生かすからです。
(新約聖書 コリント人への手紙第二 3:6)
聖書は、律法の文字に仕えるのをやめ、「御霊に仕える者」になることを促す。「御霊に仕える者」になるとは、御霊はキリストの愛を伝え、「愛の原理」によって生きられるように導かれるので、「愛の原理」によって生きることを指す。いずれにせよ、こうした教えがあるということは、裏を返せば「恐れの原理」がいかに神の福音に深く入り込んでいるかを物語っている。ならば、「恐れの原理」は一体いつから始まったのかを見てみよう。
●「恐れの原理」の起源
神は、ご自分に似せて人を造られた。ご自分の部分としてアダムとエバを造られた。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。ゆえに、彼らは無条件で神に愛されていた。彼らは神に愛されるための努力などする必要などなかったので、裸であっても恥ずかしいとは思わなかった。「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)。二人は神に愛されていることの喜びから神を愛し、互いに愛した。そこには「恐れ」などなく、「愛の原理」で生きる道しかなかった。
ところが、そこに悪魔が登場する。悪魔は蛇を使ってエバを欺き、さらにはエバによってアダムも欺かれ、神から食べてはならないと言われていた実を食べてしまった。アダムは罪を犯したのである。そのことで、人は神との結びつきを失ってしまい、神に愛されている自分を認識できなくなった。そうなると、人は自分のことしか見えなくなるので、自分の姿を意識するようになる。まるで目が開かれたかのように自分の裸の姿を知ることになる。その姿は、今の私たちが感じるように、まことに恥ずかしいとしか思えなかった。そこで、アダムとエバは何かで裸を覆い隠そうとした。
このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。
(旧約聖書 創世記 3:7)
こうして、神との結びつきを失って裸を知るようになった彼らの心には、今までなかった「恐れ」が入り込んだ。「それで私は裸なので、恐れて、隠れました」(創世記3:10)。この出来事を「死」といい、この「死」が「恐れの原理」の起源となった。この話にはまだ続きがある。
人は神との結びつきを失ったことで生きられなくなり、その体はやがて朽ちる体となった。それにより、人はいつ訪れるか分からない「肉体の死」にも怯えるようになった(創世記3:17-19)。つまり、人が覚えるようになった「恐れ」には二つの要素があった。一つは、神に愛されている自分が見えなくなったことで生じる「不安」であり、もう一つは、「肉体の死」に対する「怯え」である。こうした二つの要素からなる「恐れ」を、「死の恐怖」という。まさに、人は「死の恐怖」の奴隷となり、これが「恐れの原理」の起源となった。そこから、「ねばならない」という律法に仕える生き方が始まる。その経緯はこうであった。
●「律法」の誕生
聖書は、人は一生涯「死の恐怖」につながれ、「恐れ」の奴隷になったことを教えている(ヘブル2:15「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」)。ただし、聖書が教える「死の恐怖」の大半は、神に愛されている自分が見えなくなったことの「不安」であり、「肉体の死」に対する「怯え」は、ただそれを後押ししているにすぎない。そのことは、人が何を最も恐れているかを知ればすぐに分かる。それは「人の目」である。人からどう思われるか、人は最もそれを恐れている。その「恐れ」は、まさしく神に愛されている自分が見えないことの「不安」から来ている。「不安」ゆえ、必死になって愛される自分を目指すから「人の目」を恐れてしまう。
すなわち、「死の恐怖」は神の愛が見えなくなったことの「不安」が大半であり、そのせいで人は愛される自分を目指すようになり、「人の目」を最も恐れるようになった。自分が周りからどう思われるのかが気になり、必死になって人から良く思われようと、「この世の心づかい」に生きるようになった。イエスは、この生き方が御言葉をふさぐ「罪」になっていることを教えられた。「また、いばらの中に蒔かれるとは、みことばを聞くが、この世の心づかいと富の惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ばない人のことです」(マタイ13:22)。
では、考えてみてほしい。人から良く思われるためには何が必要かを。それは、相手の期待に応えることが必要となる。人から愛されたければ、何が何でも人の期待に応えなければならない。そのため、人の期待がそのまま心を拘束する「ねばならない」という思いになり、それがそのまま「律法」となる。
例えば、親は子どもに有名大学に入ることを期待する。そうなると子どもは、「有名大学に入らなければならない」という「律法」を心に持ってしまい、何としても有名大学に行くことで親から愛されようとする。こうして親も子どもも、愛されるための人の価値を「有名大学に入らなければならない」という「律法」で判断するようになるので、親は子どもが有名大学に入学できれば愛するが、そうでなければ怒りを覚えるようになる。まさしく人の怒りは、人が「律法」を心に持ったことで生じるようになった。「律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません」(ローマ4:15)。人に対する「敵意」の正体は、紛れもなく「律法」という戒めにあった。「敵意とは、さまざまの規定から成り立っている戒めの律法なのです」(エペソ2:15)。
このように、神との結びつきを失う「死」は人に「不安」を抱かせ、愛されたいという生き方を強いるようになり、それが御言葉をふさぐ「罪」となった。そして、その「罪の力」が「律法」を生み、人の中に怒りや「敵意」を生じさせ、人を愛せなくさせてしまった。ゆえに聖書は、次のように教えている。
死のとげは罪であり、罪の力は律法です。
(新約聖書 コリント人への手紙第一 15:56)
これが「恐れの原理」による生き方であり、この生き方は「律法」を生み出し、人を「律法」に仕えさせた。それは、「愛されたければ、○○をしろ」という生き方であり、「何々が欲しければ、○○をしろ」という考え方であり、これが「人間的な標準」の生き方となった。そのせいで、私たちは常に「何々が欲しければ、○○をしろ」と脅されながら生きている。これが「死の恐怖の奴隷」の実際であり、この生き方が神の福音に覆いを掛けてしまっている。ゆえに聖書は、次のように教える。
ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。
(新約聖書 コリント人への手紙第二 5:16)
●「愛の原理」の起源
人は元々、神の器官として造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。神の愛を十分に認識する中で神を愛し、人を愛するように造られていた。「愛の原理」の起源は、まさしく神の創造にあった。人は神に愛されている自分を認識できさえすれば、神の戒めである「愛せよ」が自然に行えるように造られていたのである。あらかじめ良い行いができるように造られていた。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
(新約聖書 エペソ人への手紙 2:10)
ところが、悪魔の仕業で「死」が入り込み、人は神に愛されている自分を認識できなくなった。そのことで、愛されるには、「○○しなければならない」という「律法」に仕える生き方が始まり、人は神も人も愛せなくなってしまった。こうして、神が語る福音にも覆いが掛かり、人は神の福音を「律法」として読むようになった。神はそうした様子を、次のように言われた。
主が彼らに言っておかれたことはこうだ。「これこそが安息である。疲れた者に安息を与えよ。これこそ憩いの場だ」と。しかし、彼らは聞こうとはしなかった。それゆえ、主の言葉は、彼らにとってこうなる。「ツァウ・ラ・ツァウ、ツァウ・ラ・ツァウ/(命令に命令、命令に命令)/カウ・ラ・カウ、カウ・ラ・カウ/(規則に規則、規則に規則)/しばらくはここ、しばらくはあそこ。」彼らは歩むとき、つまずいて倒れ/打ち砕かれ、罠にかかって、捕らえられる。
(新共同役 イザヤ書 28:12~13)
「わたしは一つの石をシオンに据える」という約束に従って来られたのが、イエス・キリストである。キリストは、「愛の原理」で人が動くよう、恐れからではなく、神に愛されている自分を知ることで行動ができるよう、「恐れの原理」を滅ぼすために来られた。そのことを、「お前たちが死と結んだ契約は取り消され」と言われた。ならばどうやって、イエス・キリストは「恐れの原理」を滅ぼし、「愛の原理」を回復されたのだろう。
●「愛の原理」を回復
イエスはこう言われた。「人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません」(ヨハネ15:13)。そして、実際にいのちを私たちのために捨てられた。それが十字架であった。私たちは罪人であったにもかかわらず、神はそのようなことを全く勘定に入れず、私たちを無条件で愛していることを十字架で明らかにされたのである。
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
(新約聖書 ローマ人への手紙 5:8)
愛を明らかにされた以上、あとは人の側がそれを受け取りさえすればよいだけとなった。ただその愛を受け取り、神に愛されている自分が認識できるようになれば、人は「愛の原理」で生きられるようになる。そこで聖書は、自らの罪を言い表してみることを勧める。そうすれば罪が赦される体験をし、神に愛されている自分が認識できるようになるからと。
もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。
(新約聖書 ヨハネ人の手紙第一 1:9)
この罪が赦される体験を積み重ねることで神に愛されている自分を知るようになり、「恐れの原理」から解放されていく。そうなれば、神を自然に愛せるようになる。「だから、わたしは『この女の多くの罪は赦されている』と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません」(ルカ7:47)。このように、イエス・キリストは十字架に架かることで、「愛の原理」を回復された。ここに、人を自由にする素晴らしい福音が見えてくる。
●自由にする福音
「死の恐怖」の奴隷となった私たちは、「ねばならない」という律法に仕えて生きてきた。神の福音もそのように読み、「クリスチャンは、○○しなければならない」といった生き方を目指してきた。しかし、そうではなかった。目指すべきは、まさに自分の罪に気づき、それでも神に愛されている自分を知ることであった。神の「全き愛」を知ることであった。そうすれば「恐れ」は締め出され、「全き愛は恐れを締め出します」(Ⅰヨハネ4:18)、神と人を「愛したい」となる。それにより、「愛せよ」に集約される「神の律法」はまことの意味で成就する。キリストは、まさにそのために来られた。
わたしが来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。
(新約聖書 マタイの福音書 5:17)
人は愛されている自分を認識できるようになると、自然に「良い行い」をするようになる。それが人であり、人はそのように造られている。「私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです」(エペソ2:10)。これが、神が人に望む「愛の原理」による生き方となるので、「また、たとい私が持っている物の全部を貧しい人たちに分け与え、また私のからだを焼かれるために渡しても、愛がなければ、何の役にも立ちません」(Ⅰコリント13:3)という教えがある。
イエスは、人が神に愛されていることを知れば「良い行い」をするようになることを誰よりも知っておられたので、いつも人の罪を赦された。そのことの最終仕上げがキリストの十字架であり、それにより「恐れの原理」から生まれた「律法主義」を終わらせた。誰であれ神に愛される「愛の原理」を回復し、信じる人はみな義とされる恵みを明らかにされた。
キリストが律法を終わらせられたので、信じる人はみな義と認められるのです。
(新約聖書 ローマ人への手紙 10:4)
まことに、イエス・キリストはイソップ童話の「太陽」であり、私たちを神の愛で包み、神の愛で生かすようにしてくださる。人を「恐れ」から解放し、自由にしてくださる。
●神の願い
だが私たちは「恐れの原理」の中で暮らすため、どうしても神の福音を同じ原理で読んでしまう。罪を犯せば、神は自分の罪を罰すると怯え、災いは罪に対する神の罰だと恐れてしまう。それは今も昔も全く変わらない。
しかしイエスは、目が見えないという災いに対し、「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神のわざがこの人に現れるためです」(ヨハネ9:3)と言われた。さらにイエスは、人をさばくために来たのではないことを教えられた。
だれかが、わたしの言うことを聞いてそれを守らなくても、わたしはその人をさばきません。わたしは世をさばくために来たのではなく、世を救うために来たからです。
(新約聖書 ヨハネの福音書 12:47)
イエスは真実を語ることで、「恐れの原理」による惑わしを取り除こうとされた。一生涯「死の恐怖」の奴隷となった人々を解放し、自由にするために戦われたのである。「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした」(ヘブル2:15)。であるから、私たちが二度と奴隷のくびきを負わされることのないよう、すなわち「ねばならない」という律法に仕えることのないよう、神は心から願ってやまない。
キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。
(新約聖書 ガラテヤ人への手紙 5:1)
人は誰であれ、「良い行い」ができるように造られていることを忘れてはならない。その「良い行い」は律法によって引き出されるのではなく、神に愛されている自分を知ることで始めて引き出される。それが、神が望まれる「愛の行い」であり、その行いには自由しかない。
|